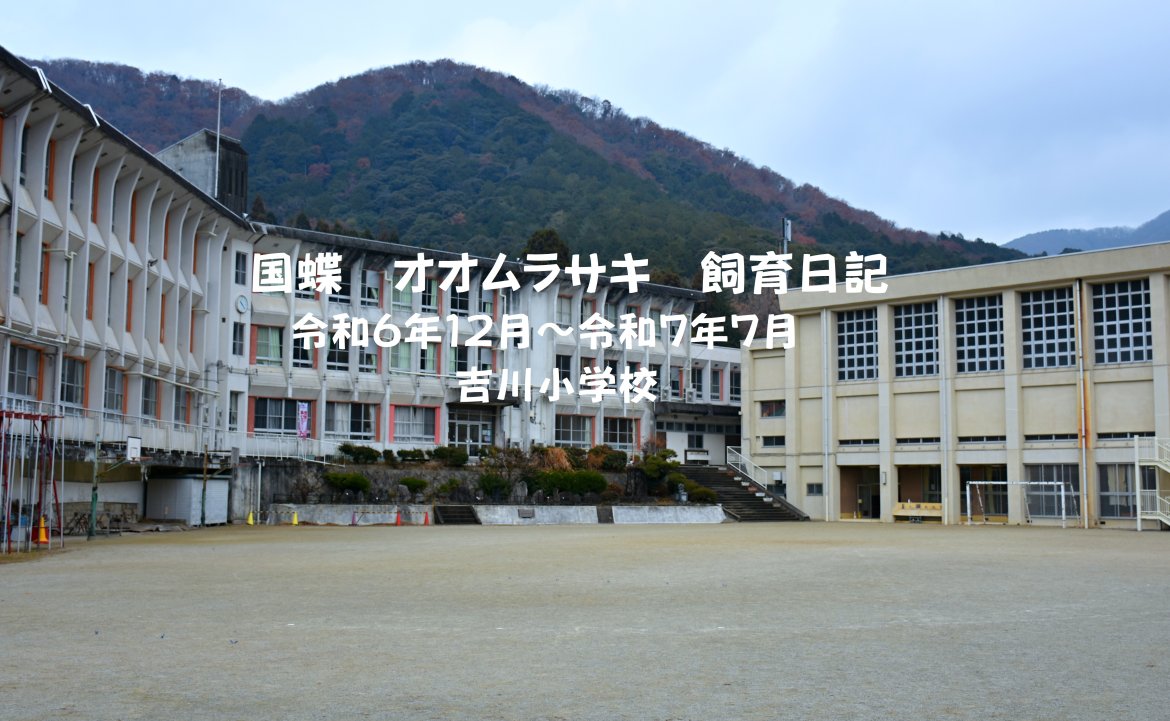6月23日、今年初めてオスが羽化。
国蝶オオムラサキ(タテハチョウ科)、準絶滅危惧種。タテハチョウの中で一番大きな蝶です。9年前から初谷渓谷で生息しているオオムラサキを、減少傾向にあったので、飼育が始まりました。その後、4年前から自然教育の一環として吉川小学校で飼育することになりました。昨年は羽化が全滅でしたが、今年はオス2頭、メス2頭、羽化しました。産卵までは出来なかったのが残念でした。豊能町吉川地区の初谷渓谷は自然環境が素晴らしく、児童たちにとって自然や命の大切を理解できる生態系の多様性の場所になっています。吉川地区のオオムラサキの生息地は高代寺山、光ケ谷にも生息しています。
昔は里山としての初谷渓谷に沢山のオオムラサキを始め、クワガタ、カブトムシ等の昆虫類が多く生息しいました。昭和30年代の燃料革命により、それまで吉川地区では炭焼きを主力に、生活の糧でしたが、炭焼の衰退により、主に炭焼の原料であったクヌギが不用になり、山の樹木・樹林の生態系が急激に変化して行きました。また、最近では、シカの食害をはじめ、特定外来生物等による様々な被害がでています。
昨年12月に、2,3年生と初谷渓谷のエノキ(落葉樹)、葉の裏に冬眠中のオオムラサキの幼虫を採取に行きました。一枚一枚葉を裏返し一生懸命捜していました。上手く幼虫を見つけた児童は自慢げに皆に見せたり、上手く見つけられなかった子供もいましたが、採取した12頭を持ち帰り、小学校の飼育ケージのエノキの下に葉っぱと一緒に置きました。文部科学省は、子供の頃にキャンプなどの自然体験や読書といった体験の回数が多いほど、自分には能力や価値があると感じる「自尊感情」や外向性などが高い傾向だったと発表しています。吉川小学校の児童達も是非この様な経験のもと、「自尊感情」の強い人間に育って行って頂きたいと思います。

12月、すっかり落葉したエノキ(アサ科、落葉広葉高木)の根元に生息している幼虫を採取しに行きました。初谷渓谷にはエノキは20本ぐらいあります。オオムラサキはエノキを食草にしています。

幼虫12頭採取して来ました。体調は10mm前後です。

この飼育ケージで育て、中に入り成長過程を鑑賞しました。

3月初旬、冬眠中、気温(10℃ぐらい)がまだ低く、エノキも新芽が出ていません。

4月上旬、気温が20℃以上になると、エノキも少し新芽が出て来て、同時にオオムラサキも冬眠から目を覚まし、木の枝に登ってきて、葉っぱが出て来るのを待ちます。保護色で木の樹皮の色と一緒で見つけにくいです。約10mmぐらい。4令で越冬します。

5月初旬、葉っぱも出て来て、余り動きしませんが、オオムラキも葉っぱを徐々に食べ始めます。

5月下旬、だんだん大きくなり、この時期になると、葉っぱを沢山食べるようになります。体調約50mm。児童もゲージの中に入って来て、保護色で見つけにくいのですが、見つけると嬉しそうにほかの児童に教えています。5~6令幼虫(脱皮を繰り返します)。

6月15日、蛹化になる。この状態の時はオオムラサキにとっては、一番無防備になる時です。外敵がこの蛹に触れると、蛹はブルブルと体をふるわせ、敵を振るい落とすようにします。しかし、天敵の蜂に産卵されることが多くあり、蛹は死にます。自分の体重を葉の裏の主脈に接着し一転で雨の日、風の日でも支えています。すごいパワーで、これをヒントにマジックテープを考案したらしいです。蛹を児童にもさわらせ、オオムラサキの生態を直接感じてもらいました。

6月下旬、羽化(写真は令和2年6月撮影のもの)。頭を下にして、全部出て来るのに5分間ぐらいかかります。その後、体液を体に送り翅を伸ばしたり、口吻を一本にしたりして体をしっかりさせます。飛び立つのは羽化後、約4~6時間後です。

6月30日、メスが羽化。体調は23cm。翅にはオスと違って青紫色はありません。オスより10%ぐらい大きい。オオムラサキの羽化は、神秘的なことがあり、オスが先に羽化し、しばらくするとメスが羽化します。

放蝶イメージ写真。今年は残念ながら、オス、メス早く死んでしまいました。
児童たちは飼育中、生態系の多様な環境の中で減少傾向にあるオオムラサキを今後どのように世代を残していくかを、情熱ある先生の教育の下で、真剣に考えてくれたと思います。
オオムラサキは蛹になるまで、5~6回ぐらい脱皮をくりかえします。蛹化した時、羽化した時、触れる児童に触ってもらい、オオムラサキとのコミニュケーションを経験しました。そのつど感動し、その時の笑顔が素晴らしかったです。
150有余の歴史ある吉川小学校は、来年3月で廃校になり、4月からは小中一貫校の豊能町立とよの西学園として新たな学校に生まれ変わります。豊能町西地区の自然は初谷渓谷をはじめ、今後、生態系は変化していくと思いますが、自然豊かな環境は残って行くと思います。新しい学校になっても、児童には素晴らしい府内でも自慢のできる環境にあるこの地区の自然を感じて勉強して頂き、多様性のある人間になって頂きたいです。